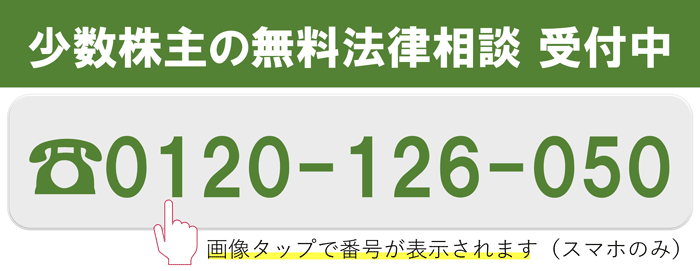はじめに:少数株式・非上場株式とは
「少数株式」、「非上場株式」の売却にお悩みの方は少なくありません。非上場株式・少数株式は株式市場が存在しないため売却の相手探しや取引価格の算定が難しく、支配株主でもないため会社全体をM&Aで売却することもできません。
- 少数株式・非上場株式を売却したいが売却先が見つからない
- 譲渡制限があるため、会社の承認がないと第三者に売却できない
- ほとんど配当がないため株式を保有するメリットがない
- 将来相続が起った場合に少数株式なのに相続税評価が高額になるのが心配
- 経営者や大株主に会社を私物化されている
こうした悩みはありませんか? この記事では少数株式・非上場株式とは何か、なぜ問題が生じるのか、売却のためのポイントや価格の算定方法について弁護士が分かりやすく解説します。
2009年 京都大学法学部卒業
2011年 京都大学法科大学院修了
2011年 司法試験合格
2012年~ 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~ アイシア法律事務所開業

Contents
少数株式・非上場株式の売却や支配株主とのトラブルは弁護士の無料相談へ
・24時間365日受付/土日祝・夜間可
・電話・Zoomで全国対応
少数株式と非上場株式の全体像
少数株式とは
少数株式とは、発行済株式の過半数に満たない少ない割合の株式を指します。保有比率が低いことで経営権や配当方針に関与しづらく、支配株主や大株主との交渉で不利な立場になりがちです。
非上場株式とは
非上場株式は証券取引所などの市場に上場していない株式のことで、売買をする際に市場価格が存在しないため、第三者への売却や正確な評価が容易ではありません。特に譲渡制限を設けている会社の場合、会社の承認が必要となり、少数株主が売りたくても思うように進まないケースが多々あります。
なぜ少数株式・非上場株式が問題になるのか
- 売却の難しさ:流通市場がなく、売却相手を探すだけでも一苦労。
- 譲渡制限の壁:会社が承認しない限り第三者に譲渡できない(会社法140条など)。
- 評価算定の複雑性:DCF法、純資産法、配当還元方式など複数の評価手法があり、結果が大きく異なる可能性がある。
- 相続税負担:配当が乏しいにもかかわらず、相続税評価が思いのほか高くなるリスク。
このように「少数株式 売却」や「非上場株式 買取」を実現しようとしても、会社側や大株主との間で交渉が難航しやすいのが現状です。
売却や譲渡承認の具体的手順
譲渡制限株式でも売れる仕組み(会社法140条)
非上場会社の定款には、しばしば株式の譲渡制限が設けられていますが、会社が第三者譲渡を承認しない場合は、会社や指定買取人が株式を買い取らなくてはなりません(会社法140条1項ほか)。ただ拒否するだけでは済まされず、まったく売れない状態に株主を置くことは法律上認められていません。
譲渡承認手続きと「譲渡承認請求書」の作成
株主が第三者へ株式を売却したい場合、まず会社に対して「譲渡承認請求書」を提出するのが一般的です。譲渡承認請求書には以下の事項を記載します。
- 1. 譲渡する株式数:○○株
- 2. 譲受予定者の名称・住所
- 3. 会社が承認を拒否する場合は会社法140条4項に基づき会社又は指定人による買取を請求する旨
- 4. 日付、請求者名(署名・押印)
会社は法定期間内(不承認の場合2週間以内等)に対応を通知する義務があり、通知せず放置すると承認したものとみなされます(会社法139条~145条)。
売買価格決定の申立て(会社法144条)
会社が株式を買い取ると決めても、「いくらで買うか」という価格面で合意できない場合があります。その際は、少数株主側が裁判所に「売買価格決定の申立て」(会社法144条2項)を行い、公正な価格を算定してもらえます。裁判所はDCF法や純資産法など複数の手法を考慮し、会社側に一方的な安値を押し付けられるのを防いでくれます。
第三者売却・M&Aを検討する余地
定款の譲渡制限がない、もしくは会社が承認してくれるなら、M&A仲介会社を使って積極的に買い手を探すという手も考えられます。業界シナジーを求める投資家や、同業種で事業拡大を目指す企業などが興味を示す場合があり、会社に買い取らせるよりも好条件となる可能性もあります。
少数株式・非上場株式の売却や支配株主とのトラブルは弁護士の無料相談へ
・24時間365日受付/土日祝・夜間可
・電話・Zoomで全国対応
株式評価の方法と裁判例
非上場株式評価が難しい理由
上場企業の株式は株式市場で価格が示されているため評価が明確ですが、非上場企業にはそれがありません。たとえば会社の将来性や資産構成、配当の有無、株主の議決権割合など、さまざまな要素が価格を左右します。特に少数株式は経営の支配力が低い(マイノリティディスカウント)という理由で、支配株主の株より低く評価されがちです。
代表的な評価手法
- 純資産法:貸借対照表の資産・負債を時価評価して算定する方法。会社の成長力を反映しにくい。
- DCF法:将来生み出すキャッシュフローを割り引いて企業価値を算定する。事業計画によって結果が左右されやすい。
- 配当還元方式:実際の配当額や配当可能性を資本還元率で割り戻して評価する手法。配当を行っていない企業では低評価になるリスクも。
- 収益還元方式:会計上の利益や営業利益を基準に株価を算定。DCF法より簡易だが、将来計画の精度がカギ。
- 類似業種比準方式:上場会社の株価・財務指標と比較する。類似企業が見当たらない場合は適用困難。
東京地裁平成26年9月26日決定
非上場会社の売買価格決定申立てで、裁判所がDCF法、配当還元方式、純資産法など複数の算定結果を調整し、最終的な株価を示した事例です。
特徴的なのは、企業の清算価値だけでなく将来の利益創出能力や配当の見込みを考慮しており、少数株式にも一定のマイノリティディスカウントを適用したうえで相応の価格を認めた点です。結果として、会社が提示していた安価な評価を裁判所が退け、少数株主に有利な売却額を確保しました。
裁判例の多様化
- 東京高裁平成20年4月4日決定:成長力が大きいベンチャー企業のためとして成長力が大きく、純資産法を採用すると株式価値を過小に評価するおそれがあるとして収益還元方式を採用。
- 福岡高裁平成21年5月15日決定:DCF法と純資産法を併用し、DCF法:純資産法=3:7の割合で折衷した金額を価格とした事例。
- 大阪地裁平成27年7月16日決定:実際の配当実績ではなく、上場会社を参考とした予想配当性向に基づき配当還元方式を適用した事例。
典型的トラブルと対策
買取価格の買い叩き
「こんな株価値がない」と大株主や会社側が低額を提示するケース。売買価格決定の申立て(会社法144条)を視野に入れて交渉すれば、一方的な安値を受け入れなくても済みます。
経営陣の私的流用・配当不払い
非上場企業だと役員報酬や親族への支出が不透明になり、少数株主に対して配当を極端に抑えることがあります。そんなときは会計帳簿閲覧請求(会社法433条)を行い、情報を把握して話し合いの材料にしましょう。
相続・事業承継トラブル
非上場株式は相続発生後に思わぬ高評価で納税負担が重くなるケースが多々あります。生前に売却して現金化するか、税理士等と連携して事業承継税制の活用を検討するのも一案です。
会社が承認を拒絶し続ける
会社法140条により、会社が承認を拒否するなら会社自身が株式を買い取る義務を負います。株主を放置して譲渡をまったくできない状態にさせることは認められず、最終的には交渉の席に着かざるを得ません。
弁護士に依頼するメリット
法令・判例に基づく交渉戦略
会社法や裁判例の具体的知識に基づいて交渉を行うことで、会社側の一方的な言い分を排除できます。自力で手続を進めると、書類不備や法的根拠の不足により交渉が振り出しに戻るリスクがあります。
書類作成や手続きのトータルサポート
譲渡承認請求書や価格決定申立書などを整合性を持って作成し、会社や裁判所に提出するには専門的知識が必要です。弁護士が代行することで、ミスやタイムロスを抑えられます。
他専門家との連携+売却候補先を探す
弁護士事務所には、税理士や会計士など相続・税務の専門家と組んで案件を進めるネットワークがあります。また、M&A仲介会社や同業界の企業とのコネクションを活かして第三者売却を検討するケースも。単に会社に買い取らせるだけでなく、より高条件の買い手を見つけるサポートができることも大きなメリットです。
多様な事例の蓄積と費用調整
過去に複数の「少数株式 トラブル」案件を扱った経験がある事務所なら、類似事例をもとに早期決着を目指せます。費用面でも、交渉型の案件なら完全成功報酬制を提案する場合があり、着手金ゼロで着手できることも珍しくありません。
少数株式・非上場株式についてよくある質問(FAQ)
まとめ・次のアクション
早めの相談が重要
非上場株式や少数株式を「どうせ売れない」と放置すると、将来の相続や経営紛争などで余計なトラブルを招くリスクが高まります。法律ではしっかりと株式売買や買取手続きの道が整備されていますので、問題を先送りにせず早期に対処することが賢明です。
当事務所へのご相談
アイシア法律事務所では、少数株主や非上場株式の売却・買取相談を無料で受け付けています。
- 四大法律事務所出身の弁護士による高度な交渉力:譲渡制限や価格決定など複雑な論点をフォロー
- 他専門家との連携:税理士・会計士と協働し、相続税・評価算定も含め総合サポート
- 第三者売却の支援:M&A仲介会社や業界ネットワークを活かし、買い手候補を探す可能性も検討
- 全国対応・オンライン相談可:遠方の方や忙しい方もお気軽にお問い合わせください
 坂尾陽弁護士
坂尾陽弁護士
少数株式・非上場株式の売却や支配株主とのトラブルは弁護士の無料相談へ
・24時間365日受付/土日祝・夜間可
・電話・Zoomで全国対応
本記事は一般的な法的情報を提供するものであり、個別の事案について法的アドバイスを行うものではありません。具体的な案件は弁護士に直接ご相談ください。